こんにちはSATOです。
今回は、映画「バビロン」を、さらに深く理解できるように、感想を交えつつ、3つのテーマに分けて考察していきたいと思います。
映画「バビロン」は、デイミアン・チャゼル監督による、2022年のアメリカ合衆国のドラマ映画です。
この映画は、ゴールデングローブ賞で5部門ノミネートして、見事に作品賞を受賞し、アカデミー賞でも作曲賞、美術賞、衣装デザイン賞の3部門にノミネートされた作品です。
ブラッド・ピット、マーゴット・ロビーが出演し、当時の熱狂や、野望と欲望を見事に演じている所も見どころです。
映画が好きな人、映画作りに関わったことがある人には、特に刺さるメッセージが込められているのではないでしょうか?
本文をお楽しみください。
映画「バビロン」あらすじ
1920年代、サイレント映画全盛期のハリウッドで、夢を追いかける青年マニーと、スターを夢見る新進女優ネリーは、運命的に出会い、映画業界で成功を掴み取ろうと奮起します。
サイレント映画の大スター、ジャックの導きを受け、マニーは映画製作に、ネリーはスターへの道を歩み始めるのですが、時代はトーキー映画へと移行し、サイレント映画は衰退していってしまうのでした。
時代の波に翻弄されながらも、夢を諦めずに奮闘するマニーとネリーは、成功と挫折、愛と裏切りを経験し、成長していきます。
果たして、最後に彼らを待ち受けているのは、悲劇か栄光どちらなのでしょうか?
映画「バビロン」は、華やかなハリウッドの裏側、夢と現実の狭間で葛藤する人々の姿を描いた、壮大なエンターテイメント作品です。
ラスト15分で映画の深みが大きく変わる。映画「バビロン」を3つのテーマに分けて考察
考察1:繊細かつ大胆な対比構造
「バビロン」で、まず素晴らしいなと思ったのは、徹底した対比構造です。
サイレント映画が極まった時代の熱狂とそれが衰退していく切ない時代、これらのコントラストがとにかく秀逸でした。
熱狂期は衣装なんてあるようでない、ほぼ裸で踊り狂う酒池肉林の様子が描かれ、移行期では優雅なドレスを見に纏い、上品なジョークを飛ばしながら会話しています。
色味もそれに合わせて赤・黄色系統の暖色系が熱狂期では用いられる一方、移行期では黒や濃紺などの寒色系が用いられていました。
映画の撮影時の対比も非常に面白かったですね。
サイレント映画ではほとんど喧嘩みたいな騒々しい中撮影し、トーキー映画では少しの音も立てられないような、静寂と緊張感のある空気感の中で撮影が進みます。
そのほかにも、いろんな対比構造が用いられていますが、何より凄かったのは時間の対比です。
コンラッドとネリーがサイレント映画を撮影をしている際は、1日の中での時間が画面上に表示され、1分1秒で目まぐるしく状況が変わりハプニングが起きる、時間の”濃さ”にフィーチャーしていました。
一方、移行期ではそれが年代ごととなり、途中からはその時代切り替えも無くなってしまいます。
映画の鑑賞者としてはジェットコースターから鈍行の電車に乗ったくらいの体感差があり、それがそのまま、時の時間の濃さに比例している対比構造になっているのは素晴らしい演出でした。
いい意味でも悪い意味でも、時代を切り拓いていくには、貪欲な欲望と何があっても突き進める勢いがある人でないとならないし、人生は決して良い時だけではないという、厳しさも痛感させてくれる演出になっていて、どちらも刺激的で楽しめました。
考察2:スターはなぜ命を絶つのか
今作は主人公が3人いました。
ブラッド・ピット演じるサイレント映画のトップに君臨する超一流ハリウッドスター、ジャック・コンラッド。
マーゴット・ロビー演じる怖いもの知らずでアバンギャルドな生まれながらのスター、ネリー・ラロイ。
ディエゴ・カルバ演じる映画製作を夢見て着実にステップアップしていく、メキシコ出身の青年、マニー・トレス。
この3人はマニーを除いて作中で亡くなってしまいます。
マニーと命を絶った2人の違いは、”生まれながらのスター”であるか否かです。
コンラッドとネリーは、その圧倒的な才を放ち、サイレント映画界のトップに上り詰めました。
そして、その圧倒的な熱量と自由で破茶滅茶な時代に愛され、彼らはその時代を愛していました。
側から見たら頭のネジが狂っていても、サイレント映画が頂点を極めた時代は、それが普通な訳です。
そして、その過激な時代はまさにドラッグのようなもので、1度味わうとなかなか抜け出せません。
しかし、トーキー映画に移り変わると、彼らの立場は危うくなり、世間から揶揄されるようになります。
コンラッドは、1度は時代の流れを受け入れようとしますが、結局自ら命を絶つことになります。
ネリーはマニーに婚約され、生きる場所を変えることであの時代を忘れることができたかもしれません。
しかし、その本能には抗えず夜の街へと消えていく訳です。
もう先の見えない真っ暗闇の時代へのメタファーですね。
華やかな生活に身を置いていると、そこから質を下げることが出来なくなってしまうのでしょうか?
天才ゆえの苦悩というのが上手く描かれていました。
一方、主人公3人のうち唯一生き残ったマニー。
彼が生き残ったのは、スターではないからです。
生まれながらにスター気質だった訳ではなく、彼は努力でその道を切り拓いてきた開拓者です。
また、映画の製作サイドの存在だったため、その熱狂を少し離れた場所から傍観していたキャラクターです。
ドラッグに溺れるシーンや酒池肉林のパーティで楽しむ様子は、ほとんど描かれていません。
だから、マニーはこの熱狂の時代に執着せずにただ、その場を去ることができたと考えられます。
マニーが映画の世界にいたのも、ネリーがずっと好きだったからというのもいいですよね。
いまだに世界のスターたちの訃報に悲しむ日がある世の中ですが、生粋のスターとは、そこでしか生きられない人なのではないかと考えさせられた、そんな展開でした。
才能や地位の高さに憧れる反面、普通でも凡人でも、強い人間であることの大切さみたいなものを感じさせてくれる作品で、とても勉強になりました。
考察3:マニーが泣いた理由
この映画は正直、残り15分くらいまでは凡作の域を出ないなという感じで鑑賞していました。
ですが、20年ほど時が経ち、最後映画館でマニーが涙するシーンで映画の質がぐんと高まり、個人的に傑作の仲間入りを果たしたと感じました。
そのくらいあの映画館のシーンは重要です。
マニーは映画終盤、映画の世界から離れ当時の熱狂とは縁遠く、幸せな家庭を築いています。
そしてきっと彼の中では、当時の映画の記憶は苦い思い出で終わっていたことでしょう。
自分が夢追い憧れていた世界は本当に正しかったのだろうかと、過去の自分を否定したい気持ちもあったはずです。
一生懸命になった事であればあるほど、挫折や後悔も大きくなってしまいますよね。
そんな時、20年以上の時が経って上映されていたのは、サイレントからトーキーへと移行した時代を舞台にした映画でした。
当時は民衆に馬鹿にされ、失敗に終わっていたと思ったものが、ちゃんと娯楽として後世に受け継がれている。
それを知ることになったマニーは、当時の熱狂や疲弊や絶望を全て思い出し、自分の夢が叶っていたことを知ります。
そうです、「映画という大きなものの一部になりたい」という夢です。
そしてこれは、ゴシップ・コラムニストのエリノアがコンラッドに言っていた言葉にも通じます。
「人としては死んでしまうが、映画があればそれは後世に受け継がれ、永遠に亡霊となって生き続けることができる」
この作品が伝えたいことはまさにこのことですね。
映画というのは今この時代で消費されるだけの存在ではなく、その時代時代の熱を誰かが受け継いで紡いでいく。
最近、名作『タイタニック」が3Dで劇場再上映になったように、当時の熱は映画という作品となり、いつまでも永遠に残り続けるんですね。
映画館で映し出される観客たちの中に、子どもが印象的に映し出されているのも最高でしたね。
著作権等でいろいろ大変だった思いますが、このシーンがあることで間違いなく映画に深みが出ました。
まとめ
以上で映画「バビロン』の考察を終わっていきます。
ゴールデングローブ賞では圧巻の評価でしたが、アカデミー賞では主要部門にノミネートされず、鑑賞前に微妙にハードルが下がっていたのですが、映画館でこの映画を鑑賞できて本当に良かったです。
映画が好きで、映画に関わる1人として、この作品のことは常に心のどこかに留めておきたいですね。
今作のタイトルになっている『バビロン』も、非常にキャッチーで個人的には好きな語呂で、終わりが、次の始まりになっているという新たな意味を付与したネーミングだと個人的には感じました。
批評サイトでは賛否両論が激しい作品ですが皆さんはこの作品どう感じましたか?
受け取り方はいろいろあるかもしれませんが、細部のこだわりや演出、俳優さん達の演技は、間違いなく素晴らしいものだったと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
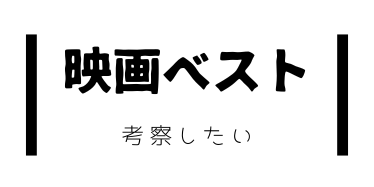


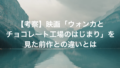
コメント